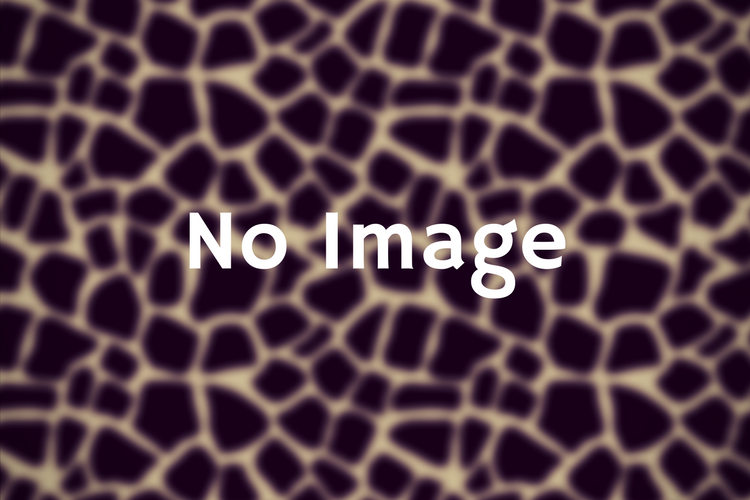#2 けげんなポール

作品集まーねは、揺れる標的。マシンガンを撃っても当たらないくせに、ネズミの射る弓矢が命中することがある。
的に付いたベルが高らかに鳴るとき、あなたの琴線に惑星が落ちてくる。
けげんなポール
塩辛いコーヒーを飲んだあと、マカダミアンは腰を据えて意見した。
「女王、ミルクのお代わりは結構です。私もナッツも、尻に火をつけられて、あたふたしている状態なのです」
女王はさっとテーブルのほこりを払い、鼻息を荒くした。
「ええ、そうでしょうとも、そうでしょうとも。その青いお尻に真っ赤な火をあぶらせて、ひーひーいっているあなたたちの顔が想像できますわ」
「早く、100本の足がついた猫を見せないと、あんたの喉にストローを突き刺すぞ」ナッツは人差し指をくるくる回しながら、女王を脅した。
「やってごらんなさい、もうすぐ、日照りの時期が来ます。けげんなポールも、帰ってきて、私の肩をもむでしょう、ほほほほ」
「ちっ」ナッツは舌打ちをして、犬歯をさすった。見事なまでのデモンストレーションだった。
椅子に座るバナナ
ジャンク・ビューは川を挟んで、ネオキ・アンダーソンの軍隊とにらみ合っていた。どちらも同じだけの兵力で、同じような兵長を従えて、同じような旗を掲げ、同じようなショッピングカートを構えていた。
ネオキ・アンダーソンはバナナを椅子に座らせた。それを新人の画家に描かせ、王国のコンテストに応募しようと企んでいた。
ジャンク・ビューはそれを見抜き、脂の乗った結婚指輪を椅子に座らせた。指輪を強奪された兵士は、目まぐるしく宴会を開いた。これではあのパンクフットの料理長のようになる。
錯乱した兵士を友人はなだめた。
「もしお前の主人がネオキ・アンダーソンなら、いまごろ全身の毛を剃られて、女の子みたいに可愛くさせられてしまうぞ、感謝するんだな」
兵士は血走った目を日記帳に書き、その友人の言葉を飲んだ。傷ついた名誉はもう戻らない、たった1回のショッキングで夢を見ることはできなくなる。
強張った文字列を見直そう。シンプルな大吉は、やがてライオンの心臓となるであろう。
片目のオアシス
与えられた部屋を、システマチックに歩くたびに、ナッツはため息をこぼした。マカダミアンはベッドに横になって、「あくまでも創造の世界」という本を読んでいた。
ナッツは壁に画びょうを刺して嫌がらせをした。100本の足の猫なんて、大したことなかった。足が100本あるだけだ。顔が100もあるわけじゃない。どうしてあんなに修学旅行生のようにはしゃいでしまったのだろうか。これでは味噌のカスにもならない。
「具体的にいうとさ、あの女王の脳みそはクッパでできている」
「証拠は?」マカダミアンは本をめくりながら、どうでもいいようにナッツにそう聞いた。
「どこもかしこもおかしいからさ。それにクッパの匂いがする。あの服にも染みこんでいるんだ。ぼくは鼻が利くからね。昔、それが原因で兄弟がハンカチをくれたよ」
「優しい兄弟だ」マカダミアンは無意識に皮肉をいった。
こんこん。だれかがドアを叩いた。ナッツが開けてやると、ドアの前に金髪の少女が立っていた。ナッツはくんくんと匂いを嗅いだ。
「あんた、女王の娘だな、なにをしにきた。ルームサービスは頼んじゃいないぜ」
「母のことを許してほしくて、非礼をお詫びします。マカダミアン様にナッツ様。母はただ、歯並びが悪いだけなのです」娘はいまにも泣きそうにしていた。
「へえ、歯並びが悪いのは重罪だぜ、頭がクッパなのはぼくたちの村じゃあ死刑になる。あんたわかってんのか?」ナッツの声に、娘は小さな悲鳴を上げた。
マカダミアンは本から目を話し、娘をどうしようか考えた。
これがシナリオ通りなら、あの娘を殺さなくてはいけない。だが、私は順序を守らない。だとすれば、答えはひとつだ。
マカダミアンは狂気に震えた。エチケットを守る輩はそう多くない。沈む夕日に感謝する人がこの世に存在するだろうか。存在するなら、その人は、神のごとき歯並びをしているに違いない。